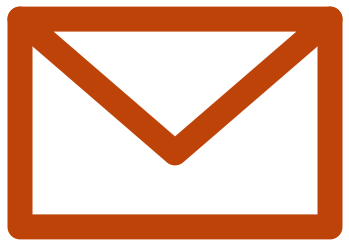前科を付けない為にすべきことを弁護士が解説

あ
本コラムでは,有罪判決を受けて前科がつくことによる影響や,前科をつけないためにどのようなことをすべきか解説します。
目次
1、前科、前歴とは?
「前科」,「前歴」という言葉について,明確な法律上の定義はありません。
あ
一般的に,「前科」とは有罪判決により刑が言い渡された事実のことをいい,「前歴」とは,警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査の対象となった事実をいいます。
つまり,逮捕や取り調べは受けたものの不起訴となったような場合も前歴に含まれることになります。
2、前科がつくことによる影響
会社の就業規則等に、有罪判決を受けることが「解雇事由」として明記されている場合、解雇される可能性が高いといえます。
あ
また、就業規則に前科についての規定がなくても,犯罪事実や所属先が報道されることで会社の名誉や評判を著しく傷つけた場合や,犯罪行為の性質,態様などから会社や他の社員等との関係で職場環境を強く害するといえる場合は,解雇の正当な理由となり得ます。
あ
解雇までされない場合であっても,何らかの処分を受けるということは十分考えられます。
(1)職業や資格の制限
前科がつくと、一定の期間、就業できない職業や、取得できない国家資格があります。
具体例は以下のとおりです。
あ
(ⅰ)弁護士,公認会計士,弁理士などの士業
禁錮以上の前科の存在は欠格事由となりますので、一定期間内は就業できません。
(ⅱ)国家公務員・地方公務員
公務員も禁固以上の前科があることが欠格事由となります。
(ⅲ)警備員
警備業法により、禁錮以上の前科を有する者は刑の終了から5年間警備員の仕事につくことができません。
(iv)その他
貸金業者や,医師,歯科医師,薬剤師などもそれぞれの業法の下,前科が欠格事由と定められています。
(2)就職活動で不利に働く場合がある
まず前提として、法的に前科の有無というプライバシー性の高い事項を申告する義務はありませんので、これを秘匿することは自由です。
しかし、履歴書の「賞罰」を記載する欄がある場合,前科がある場合は記載をすることになります。
あ
後述するように前科を欠格事由とする職業では必然的に前科の申告が必要です。
前述の通り、真実を告知する義務は法的にありませんが、就業規則等で「採用時における虚偽の告知は、解雇事由に該当する」などと定められている場合、採用時に前科の有無を偽ったことを理由として、就職後に解雇されるおそれがあります。
あ
また、前科を秘匿した上で採用され、採用後に前科の事実が発覚した場合、解雇を免れたとしても、経歴詐称として事実上の不利益を受ける可能性は否定できません。
あ
もっとも、正直に申告したことで、採用されないというリスクはあります
(3)海外渡航の制限を受ける可能性がある
パスポートが失効するということはありませんが,新たなパスポートの発行(旅券法13条)がされない,諸外国でビザの発給ができないなどの影響が考えられます。
(4)私生活や親族への影響
事件が実名報道をされた場合は,近年のネット社会の下犯罪をした事実が半永久的にインターネット上で記録される可能性があります。
あ
そうなると,自身の人生のみならず,家族や親族も「犯罪者の家族,親族」という見方をされるおそれがあります。
3、前科を付けないためには
犯罪事実について本人が認めている場合や,客観的証拠により明らかな場合は起訴されると有罪と判断される可能性が非常に高くなります。
あ
そのため,前科をつけたくない場合は起訴前に示談等を行い,不起訴処分を目指して活動を行うことになります。
4、不起訴処分を得るためには
刑事事件について起訴をするか不起訴とするかの判断は検察官が行うことになります。
つまり,不起訴となるためにはその判断をする検察官に対し不起訴とすることが相当であることを示す必要があります。
あ
検察官が起訴又は不起訴の判断をする際の基準は明確に示されているわけではありません。
一般的には,検察官が起訴にするか不起訴にするかは,犯罪行為そのものの悪質性や被害者の処罰感情,被害者側との示談の成否や被害弁償の有無,本人の反省の程度や再犯可能性の有無といった諸事情を総合的に考慮して判断をしていると考えられます。
(1)被害者との示談交渉
検察官が起訴・不起訴の判断をする際の考慮要素の内,被害者との示談が成立しているかは重要な考慮要素となります。
あ
そのため,検察官が起訴・不起訴の判断をする前に,速やかに被害者と示談の交渉を行い,示談を成立させることが望ましいといえます。
(2)検察官との交渉
被害者との示談が成立したら,示談書を作成し検察官へ提出します。
あ
その上で,被害者との示談が成立していることや,被疑者本人が反省をしていること等,被疑者側に有利な事情を伝え,不起訴処分が相当であることを伝え交渉をすることになります。
5、無実の罪で逮捕されたら
万が一身に覚えのない事件で逮捕をされた場合,取調べで明確に犯罪事実を否定することが必要です。
あ
厳しい取調べから逃れるために自白をしてしまった場合,その自白とその他の証拠から起訴され,有罪判決を受けた場合前科がついてしまうことになります。
(1)事実でない供述をしない
逮捕後,警察官や検察官から取り調べを受けることになります。
取り調べは,受ける側にとっては精神的にも苦しいものであり,事実関係を認めてしまえば楽になる,身柄拘束からも解放されると考え,事実と異なる自白をした場合,その自白が起訴をする際の証拠にされることになります。
あ
厳しい取調べがなされたとしても,事実と異なることは話さないことが重要です。
(2)不利な供述調書に署名しない
また,取調べの内容は供述調書という形で書面にまとめられます。
取調べ後にその調書の内容を読みあげ,内容に誤りがないかを確認する手続があります。
あ
調書に記載された内容に自身の認識とは異なる部分,特に自身に不利益となる内容が含まれていないかをよく確認する必要があります。その上で,少しでも納得できない部分があれば,訂正を求め,安易に署名をしないことが重要です。
6、不起訴処分となった事例
過去の事例でも,窃盗被疑事件等の被害者がいる事件において,起訴前に迅速に被害者と示談が成立し,不起訴処分となった事例があります。
あ
不起訴処分を獲得するためには,被害者との示談の成否が重要なポイントになります。
7、前科を付けない(不起訴処分を得る)ために当事務所にできること
犯罪を起こしてしまった場合や罪を疑われた場合、早めの対応が必要となります。
あ
上述の通り,逮捕前や起訴前に,被害者との示談交渉をし,示談を成立させることは不起訴処分を得るための重要なポイントの一つとなります。
また,しっかりと反省し,再犯をしないような態度を示すことも大切です。
あ
前科を付けないようにするためには,まずはどのように対応すべきかアドバイス弁護士に相談することをおすすめします。